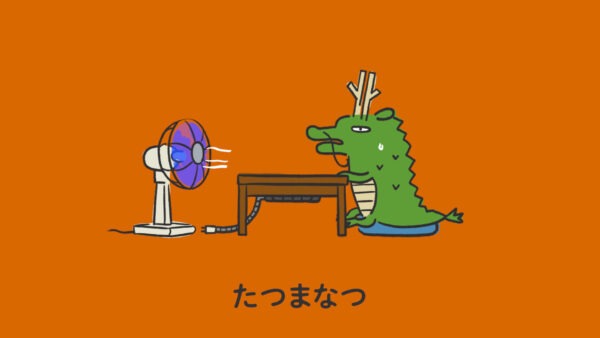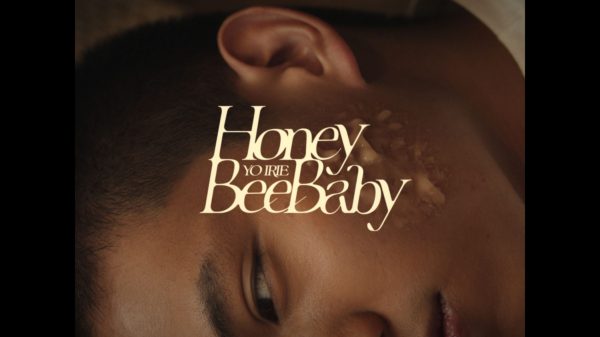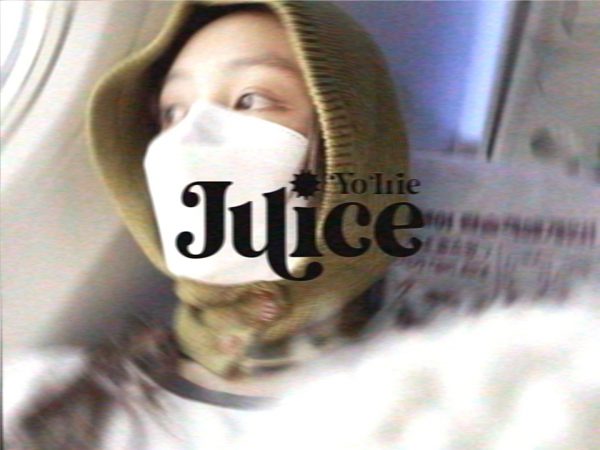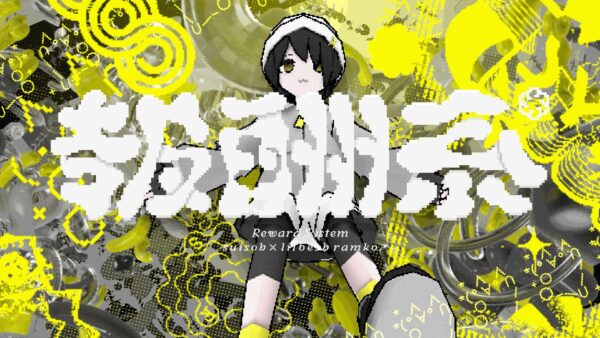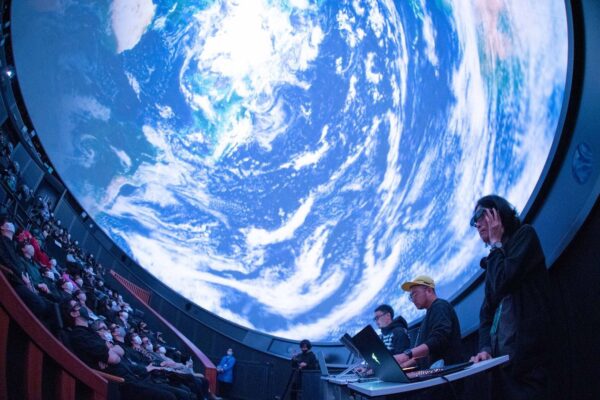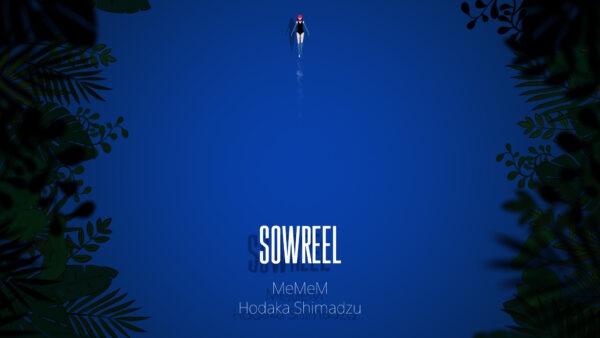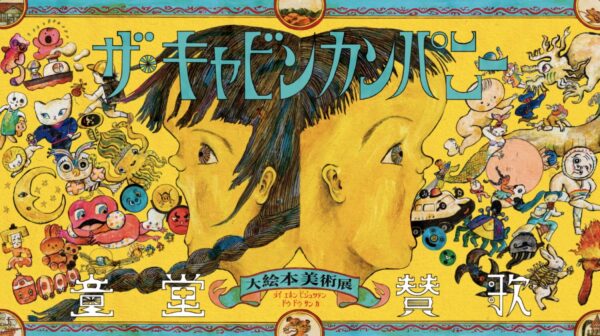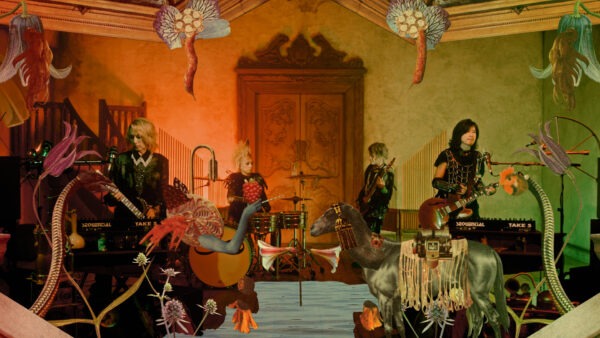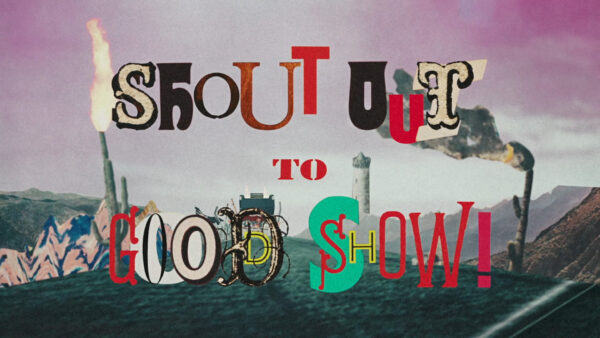-
映像作家100人2025

-

“BOKURA WORKS” 2025 Autumn/Winter プロモーション
Luna Terasaka
-

今此処
Yaoyoro's Aki
-

第四回 文字とクラブ
Toshiki Okamoto
-

Sennzai – Monochrome
Shion SHIMADA / Salis
-

TEMPURA MAGAZINE 2024
SEIKO
-

「桃源郷とタクシー」 MLA2025 Visual Edit
TAMURA Ikuho
-

ムーンゲイザー
Toshiki Okamoto
-

monoton VJ Reel 2024
monoton / Haruma Tasaki
-

Dialogues in Form – monoton
monoton / Haruma Tasaki
-

The Indifferent Window
Popular
SEE MOREMovies
Loading...
No more content
Error loading content
Loading...
No more content
Error loading content